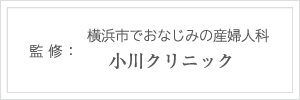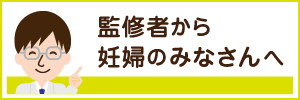現代の日本は、「安全・安心」にとても熱心です。
戦後の経済成長、社会の発展とともに清潔で安全な社会を追求してきた日本人にとって、安全を求める欲求はいまや当然の権利のようになっています。それは妊娠・出産においても例外ではありません。
実際に、この30年で産科医療の診療法や医療技術は目覚ましい進歩を遂げ、妊娠・出産時の妊産婦および子どもの死亡率は、劇的に低下しています。
母子保健統計のデータでは、2015年の出生10万人あたりの妊産婦死亡率(妊娠中から産後42日未満の死亡率)は、3.8人と史上最低を記録しています。厚生労働省の人口動態統計(2014年)でも、出生1000人あたりの周産期死亡率(妊娠22週目以降の死産および早期新生児死亡)は3.7。これらは世界的に見てもトップレベルの数値です。
こうしたことから現代日本の妊娠・出産の“安全神話”が生まれてきましたが、一方で、新たなリスクも生じています。
それは安全を追求し続ける社会の中で、妊娠中の女性やその家族といった当事者ですら、「お産は命がけ」という認識がどんどん薄れてきていることです。
日本でも、今から60~70年前は、妊娠・出産の状況は現在とはまったく異なっていました。昭和20年当時の日本の妊産婦死亡率は実に現在の約50倍、新生児死亡率に至っては、現在の約80倍もの高さだったといわれます。
当時はもちろん、自宅分娩で衛生状態も違いましたし、妊婦管理や超音波検査のような医療技術も、現在とはまったく異なっていました。しかし、どれだけ衛生状態や医療技術が進歩しても、妊娠・出産のリスクをゼロにできるわけではないのです。
たとえば、昔の産婦の多くが命を落とした疾患に産褥熱(さんじょくねつ)があります。
これは、産後数日した頃に細菌やウイルスに感染することで起こりますが、命を落とすまでに重症化してしまう最大の理由は、妊娠中から産褥期にかけての母体の状態にあります。妊娠中は免疫機構そのものが大きく変化していて、細菌などの感染から母体を守るシステムが一時的に弱まるタイミングがあります。そこで感染を起こしてしまうと、高い確率で命を落とす結果になってしまうのです。
現在でも、日本やアメリカ、ドイツ、イギリス、フランスといった先進国から、アジアや中東、アフリカの発展途上国も含めて計算した統計によると、全世界平均で約250人に1人の女性がお産で命を落としています。日本でも、周産期に命を落とす女性の人数は、実は交通事故で亡くなる人の数にも匹敵します。
こうしてみると、お産は今の時代でも「安全」とはとても言えません。むしろ命に関わるトラブルに遭わずに済んだ場合、「たまたま運が良かった」と考えるべきでしょう。